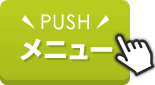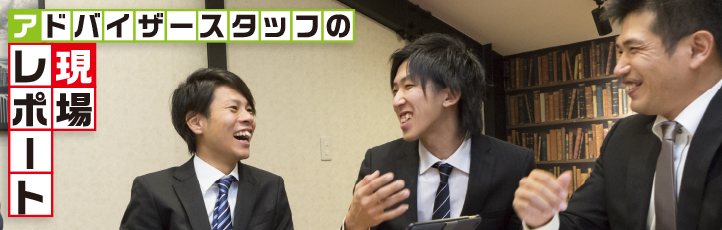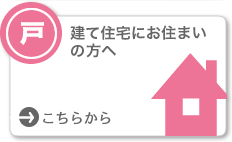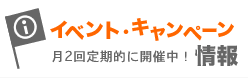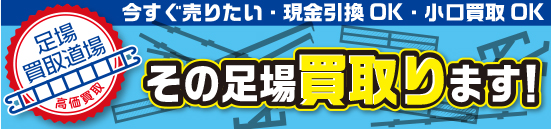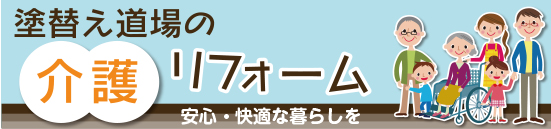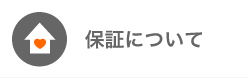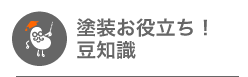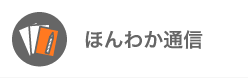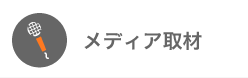こんにちは!
ここ最近は真夏のような日差しになることも・・・(^▽^;)
大規模修繕における現場では、水分補給がとても大事な季節となってきました。
今回のブログでは、外壁塗装前に欠かせない修復のお話をしたいと思います!
クラックをそのままにしてはいけない
外壁にできるヒビ割れのことをクラックといいます。
クラックを放置しておくことは建物に悪影響を及ぼし、老朽化を早めてしまう原因につながり兼ねません。いくらそのあとの塗装に力を入れても、基礎ができていないと品質は低いままになってしまいます。
そんなクラックにも種類はさまざま。
まずは特に業者に頼むべきとされている、危険なクラックの種類をみていきましょう。
■構造クラック
地震などによる揺れによって外壁材に影響を及ぼし、建物の構造的な欠陥となってしまうもの。基本的に、幅0.3mm、深さ4mmの以上のクラックは、基礎の補修が必要です。
これは表面だけでなく内部の鉄筋にまで届いてしまっている危険な状態なので、できるだけ早く業者さんにみてもらうようにしましょう。
■乾燥クラック
外壁工事の際、塗料の乾燥過程で発生する幅の狭いひび割れのことです。
■ヘアークラック
幅0.3mm以下の髪の毛のように細いひび割れのこと。塗膜の劣化や塗料の乾燥時間が足りなかったことが原因で起こりやすいクラックです。
Uカット補修のおこない方
このようなクラックの補修に利用されるのがUカット補修です。適用されるのは0.3mm以上のクラックがある場合。0.3mm以下の場合は、シール工法というものでおこなうのが一般的です。Uカット補修は、クラックに沿ってU字のように溝を掘り、そこにエポキシ樹脂を投入していく方法です。
1、フィラー処理
その他、フィラー処理という補修方法も有効的です。フィラーとは、超微粒子セメントであり流動性も抜群な優れもの。クラック部分を水で濡らしてから、フィラーを少し盛り上げるように仕上げていきます。硬化後はその盛り上がりを削り、綺麗に仕上げて補修が完了。Uカット補修より手間がかからず、比較的短時間でおこなる補修方法です。
2、 エポキシ注入
Uカット補修やシール工法に比べて、クラックの深層部まで補修できるのがエポキシ樹脂の注入です。構造上主要な壁や壁面を貫通している大きなクラックの場合に有効です。
ただし、この補修が直接耐震強度に影響するかどうかといったら、そうではありません。あくまで、保護剤の欠落防止につながる工事なので躯体とは別になってくることを忘れてはいけません。
3、爆裂補修
そもそも爆裂とは、クラックから雨水が侵入しコンクリートの建造物に錆が生じたことにより、コンクリートが膨張して押し出された状態になること。これを放置すると、建造物自体がもろくなってしまうので早急に補修が必要です。まずは発生してしまった錆を落とし、鉄筋を露出させてブラシなどで錆を落としていかなければなりません。原因は錆なので、錆止め塗料などを塗布し、防錆処理をおこなっていきます。防錆処理後は建築材料において仕上げの役割を担うモルタルを塗布し、綺麗に整えていきます。
4、タイルの浮き修復
大規模修繕がはじまり、建物全体の調査が行われたときに想定外の不具合が発見される場合があります。その中でも多いのが、タイル浮き・剥離です。外壁としてとても見栄えのいいタイルですが、剥離してしまうと、住人や通行人の方にケガをさせてしまうことも考えられ、大変危険です。タイルの浮きは特に手抜き工事によって施工された場合に多く見受けられます。
■修復は注入をおこなう!
タイルの浮きが確認された場合は、目地(タイルとタイルの間の部分)の部分に穴をあけ、接着剤を注入するのが基本です。しかし、その浮きが広範囲に及ぶ場合はタイル全体を張り替えなくてはいけません。
■浮きやひび割れたタイルには新規張り替えを
全体の張り替えを行う際でも、どの部分にどれくらいの量を注入するかという工法に気を遣うことが大切です。
タイルは、綺麗な状態を保つことでその建物の安全性も確保しています。こまめに綺麗に修復していくことで、部分的な張り替えで済むこともあるので、本格的に劣化する前にしっかり補修をしていきましょう。
■同じ色・デザインのものを特注する
張り替えるにしても、既存のタイルと同じものでないと美しくありません。タイルは1窯で大量生産が可能なので、今後のためにも多めに発注しておくと良いでしょう。
つなぎ目の隙間を埋めるシーリング工事
外壁塗装をするうえで、シーリング工事も欠かせません。
建物の外装にできるちょっとしたつなぎ目の部分(目地)にシーリング材注入することで、雨水やほこりなどが入ってくることを防ぎます。
1、外壁目地(打ち継ぎ目地・スリット目地等)
打ち継目地とは、コンクリートの継ぎ目の部分のこと。シーリング材を充填するための目地は、打設時にあらかじめ作られるようになっています。それに対して構造スリットとは、コンクリート構造のフレームにしなやかさを持たせるために柱と壁、梁と壁の縁を切るために設けられるものです。
2、タイル目地
タイル目地とは、タイルを貼り付けたときにできる部材同士の隙間のこと。ここにもシーリングを充填することで、タイルの剥がれなどを防ぎ外壁を綺麗に保つことができます。