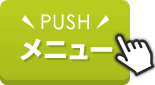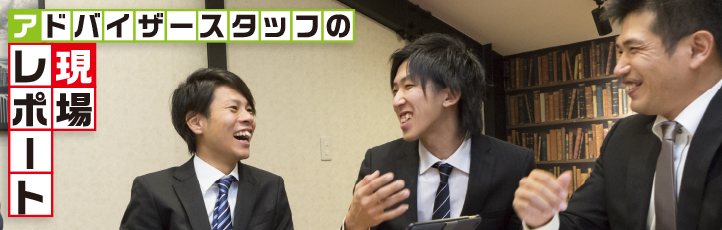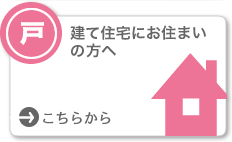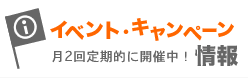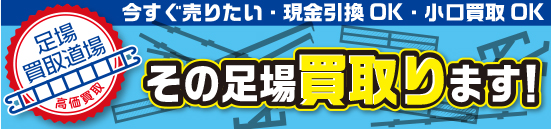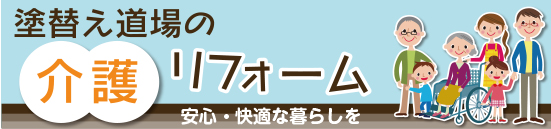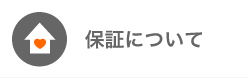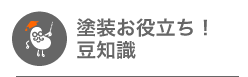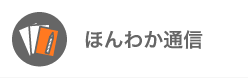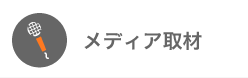「塗替え道場」が配信している「塗替えTV」の動画から「クリア塗料」の動画をご紹介です!
クリア塗装とは?
色がない塗料を使用した塗装なのですが、模様の入った変わった外壁を塗っていきますよ。
透明ならではのメリットや塗装が可能な条件など、いつもと違った塗装をお伝えします!
気になる動画はこちら!
↓↓↓
【魔法の塗料で新築に】色のない塗料で外壁を守るクリヤ塗料で外壁を塗ってみた!
毎日、配信していますので、ぜひチャンネル登録よろしく~!
塗料なのに色がない?!
ザッス!
いまいち流行らない挨拶で始まりました!
戸建てのお宅で塗装工事ですが、今回塗る外壁はいつもと違います。
模様が入っていて、目地がある!
通常、外壁を塗る時は「塗りつぶし」という工程です。
色見本を持ってきて「何色にしますか?」という風に色の提案をして色決めをします。
今回のような目地があって柄がある外壁はベタ一色にしてしまうともったいない!
ぼかしも入っていてとってもオシャレな外壁ですよね!
このような外壁の時はクリア塗装をおすすめしています。
クリア塗装とはその名の通り透明で色のない塗料です。
これで外壁を塗ると透明なので色が付かず、外壁の模様や色がそのまま見える!
なんとも不思議な塗料なのです。
そのままが見えるので、もちろん傷や汚れなども見えてしまいます。
なので、全ての外壁に塗装ができるわけではありません。
このクリア塗装をする時はどのような時なのでしょうか?
クリア塗料ができる条件
ここでクリア塗装ができる条件をお教えします!
まず、外壁が傷んでいないこと。
これが第一条件です。
もし、傷んでいても少しならOK。
多少の傷ならば、タッチアップ(補修)で何とかなります。
けれど、キレイに塗るためには極力傷んでいないことが望ましいです。
シーリングの色も良く見ると目地に似せていますね。
いつもは白で打っていますが、色を付けているのです。
このように外壁をそのまま残して美しい状態にしますので、塗り替えのタイミングは早めの方がいいですよ!
外壁の塗替えは傷んでからするイメージがありますが、痛みや経年劣化が目立たないうちに行うのがクリア塗装のベストタイミングです。
今回のお宅は10年くらいだそうですよ。
痛みが少なく良い状態。
けれど、外壁の傷みは立地条件でも変わってきます。
近くに湿気を保つような環境がない方が良いそうです。
日陰になる部分が多いのもダメですよ。
今、この外壁は1回目の塗装が終わったところですが、濡れ感出ていてとてもキレイですね!
ツヤツヤしています。
ではこれから塗るところをお見せしますよ!
れっつらご!
塗り方のコツを解説!
今、塗っていない外壁の前に来ています。
上が塗ってあって、下がまだ塗っていません。
色がないから塗られているかどうか、非常に分かりづらい!
では、塗りま~す。
分かりますか~?ちょっとカメラ越しでは伝わりにくいですね。
カメラアングルを下からにすると濡れているかのようなツヤが見えます。
ここで、クリア塗装のコツを。
色が付いていないので塗料が垂れるのが見づらい、という困った問題があります。
なので、あまり付け過ぎないように。
重ね塗りをして少しずつ伸ばしていきましょう。
通常の色塗料と同じく、縦に配って横に伸ばす。
目地の塗り残しがないようにしっかり塗ります。
そして、角度を変えて見てみましょう!
自分が塗ったところは全部反射しているので分かりづらいです。
横から見て塗れているかどうか、塗残しがないかを確認しましょう。
じっくり横から…寺西くん!顔!
どんな顔で見てもいいですよ!
確認してくださいね☆
塗り残しにならないためには
塗り残しがでやすいクリア塗装。
何といっても目地が塗り残ししやすいです。
奥まで塗料が入っていない状態になりやすい。
そして塗装と塗装の繋ぎ部分です。
上から塗って、下りてきますが足場の下までクリア塗装の場合は塗ります。
下の人がその上から被せて塗れるようにするためです。
声を掛け合いながら、どこまで塗ったかを確認しつつ塗り残しが出ないように塗っていきます。
1度塗っただけでこのツヤですので、これで終了~。
ではないのです!
塗り重ねることで更に強くなり、ツヤが出ます。
なので、メーカー指定の回数を絶対塗らないといけません。
クリア塗装は2回塗りをして、ちゃんと膜厚を付けていきますよ。
とにかく、「垂れ」と「塗り残し」に気を付けることが重要です!
そして使用する道具はローラーですが、これは気泡が出にくいローラーを使用します。
塗っているとブクブクと泡が出るものがあるそうです。
それは適していないローラーなので、気泡が出ないものを探してくださいね。
「こんなにキレイな仕上がりならうちもやってみたい!」と思った方もいるのではないですか~?
でも、この塗装は高そうじゃないですか?
実は通常の塗料とクリアの塗料、そんなに金額は変わらないそうです!
ただ、手間がとってもかかるので職人さんは大変…!
何が大変なのかというと、天井とクリア塗装の境目を塗りこむことができません。
本来は天井を先に塗って、ちょっと壁側に塗料を被せます。
付帯部(樋や軒天など)の色が外壁の方に付いてしまわないよう、最新の注意を払わなければなりません。
通常なら、塗料が付いてしまっても上から塗ることができるのでいいのですが、クリア塗装は何といっても透明!
上から塗っても隠せませんので、付かないようにしないといけないのです。
紙テープをしっかり貼って養生するのもいいのですが、下から塗料が潜ってしまう可能性もありますので、信用しきれないですね。
なので、刷毛でしっかりと刷毛取りする必要があります。
ずっと刷毛で線を引いていくので、塗りつぶし塗装にはない手間がクリア塗装にあるのです。
そのような細かい作業がありますので、当然スピードも落ちます。
時間がかかる塗装ですが、仕上がりは最高ですね。
クリア塗装の注意点
手間がかかるクリア塗装ですが、塗装する上での注意点があります。
寒い季節によく起こる現象なのですが、「ブラッシング現象」というものがあり、これになってしまうと大変!
寺西くんは体験したことはないそうですが、かなり困った状態なってしまうそうです。
乾いている時に一気に気温が下がると、起こる現象です。
特に夜間などに起こり、昼間急いで塗って夜に冷え込んでくると…。
次の日、塗ったところが真っ白に!
「塗料が乾燥する前に空気中の水分が付着し、そこが凹凸になることで光が乱反射して曇って見える現象」をブラッシング現象といいます。
せっかく塗ったところが白くなってしまうので、白い部分を研磨して塗装をやり直しや、最悪な場合は塗りつぶしなってしまうことも。
なので、気温や塗り重ねなどのタイミングが非常に重要になってくるのです。
壁の一番下まで塗れたら、水切り部分は刷毛取りします。
傷みがない外壁にクリア塗装ができるといっていますが、レベルとしてはチョーキングが起きていない状態であることが大事です。
触った時に塗料が白く付いてくることがあるのです、それが起きていない、もしくはほんの少しだけ。
そして目地がキレイでかけたりしていないこと。
もし傷みがある外壁に塗装しても、その状態が保たれるだけなのであまり良くありません。
「家を守る」という塗装なので、見た目が変わって気分も変わるだけの塗装とは一味違います。
いつまでも新築の状態を保つためにはクリア塗装が大事です!
と、寺西くんがドヤ顔で言っていますが、カメラマンさんのコメントをパクっています。
コメント泥棒ですが、罪悪感は0!
お疲れ様でした!
次回は「養生」の解説動画をご紹介。
足場職人・ミッチーと寺西くんの対決も見ものです!
養生をいかに早く・丁寧に行うかを解説します。
お楽しみに~☆
また見てね~。